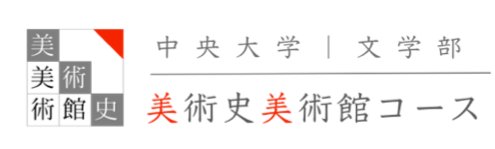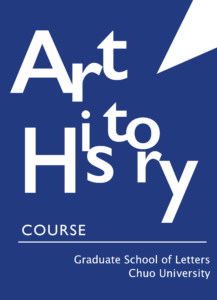
大学院には、美術史コース*があります。
美美コースからスムーズなつながりがありますが、ひとつ上のレベルで学びます。
学部での学びを基礎に、もう一歩ステップアップして社会に出ることをめざします。
*2025年度博士前期課程入学者より適用
NEWS
- 2025年春より、新たに3名が大学院美術史コースで学びます。美術史専攻の院生は、6名となります。 Apr. 1
- 2025年春より、本専攻修了生2名が新たに
 藤田美術館(大阪)、
藤田美術館(大阪)、 泉美術館(広島)に学芸員として採用されました。 Apr. 1
泉美術館(広島)に学芸員として採用されました。 Apr. 1 - 今年行われる入試の日程が公表されました。
 こちらからご覧ください。 Mar. 14
こちらからご覧ください。 Mar. 14
大学院とは
- 大学院は、博士前期課程(以下では「修士課程」と記載します、2年間)と、その後の博士後期課程(同じく「博士課程」、3年間)に分かれています。修士課程を修了した段階で就職するのもごく一般的で、この場合も中退ではなく修了(学部の卒業にあたります)となります。学部から修士課程に進学する際、また修士課程修了後に博士課程に進学する際には、それぞれ入学試験があります。
- 修士課程では修士号(Master)、博士課程では博士号(Doctor)を取得できます。
- 公務員や教員の場合、修士号、博士号を持つことで学部卒(学士号)とは待遇がことなります。一般企業等でも、これに倣う場合が少なくありません。
大学院美術史コースの学びとは
- 大学院では、美術史という専門に集中して学び、研究成果をあげることを目指します。そのため学部と異なり、履修する科目数は抑えられており、必修の外国語や一般教養等はありません。修士課程の場合、週に4科目程度履修することになります。美術史関係科目に加えて、フランス語・フランス文学の科目や他専攻(西洋史関係科目など)の科目、美術館でのインターンシップ(下記)を履修することもできます。履修プランは、担当教員と相談した上で決めます。
- 中央大学大学院文学研究科仏文学専攻修士課程では、「美術史コース」に所属して美術史を専門として学ぶことができます。学部の美美コース専任教員が大学院科目と研究指導を受け持っています。指導にあたっては、受講生の研究テーマに合わせて授業内容を決めます。
- 授業の形式は、セミナー形式です。一方的な講義形式の授業は、基本的にありません。授業は通常、受講生1〜4名程度で開講され、書物や資料を元に教員とともに考え、研究を進めるのが大学院の学びのスタイルです。この過程で専門的な考え方、掘り下げ方、調べ方、伝え方、まとめ方を実践的に学びます。受け身に学ぶのではなく、主体的・能動的に掘り下げる姿勢の涵養も目標です。ときに、学外に見学に行くこともあります。外部講師を招いての講義・講演を行うこともあります。
- 授業のほか、ひとりひとりの研究指導を行い、学位論文(修士論文、博士論文)の執筆をめざします。研究テーマは、教員の専門分野であるフランスを中心とする西洋近代美術史からテーマを選びますが、「フランス美術と日本との関わり」といった横断的なテーマを設定することもできます。
- 大学院間の協定により、
 学習院大学大学院人文科学研究科・美術史学専攻で開設している美術史関係科目を履修して、単位を修得することができます。
学習院大学大学院人文科学研究科・美術史学専攻で開設している美術史関係科目を履修して、単位を修得することができます。 - 2024年春には、美術史を学ぶ院生による読書会+自主ゼミ「ヨミゼミ」が発足しました。美術史の古典的な文献を取り上げた読書会を開くほか、展覧会情報などを共有しながら楽しく自発的に学んでいます。指導教員以外に、先輩、同輩から学ぶ部分が大きいのも大学院の学びの特徴です。
カリキュラム
修士課程|修了単位32単位
- 必修科目:16単位 *必修の4科目(各2単位)は、1年次、2年次を通して2回ずつ履修して、計16単位修得します。内容やテキストは、毎年変更します。
- フランス近代美術史演習A(阿部成樹)…主に18世紀から19世紀のフランス美術史を扱います。
- フランス近代美術史演習B(阿部成樹)…履修者の研究テーマに合わせて研究発表の技法を発展させます。
- フランス近代美術史演習A(泉美知子)…主に19世紀から20世紀のフランス美術史、文化遺産の歴史を扱います。
- フランス近代美術史演習B(泉美知子)…主にフランス語美術史文献の読解を行います。
- その他履修科目(選択履修):16単位
- インターンシップ(美術館実務研修)…美術館における院生向けインターンシップを受講して、学芸員に向けての実践的訓練を積みます。
- フランス語学・文学関係科目(フランス古典啓蒙文学演習、フランス近代文学演習、フランス現代文学演習、フランス詩演習など)
- 他専攻開講科目(西洋史学関係科目、浮世絵学、マンガ論、アカデミック・ライティングなどを推奨)…12単位まで履修可能
- 単位互換協定のある他大学大学院開講科目(西洋美術史、日本美術史関係科目を推奨)…15単位まで履修可能
博士課程|修了単位16単位
- 必修科目:12単位|指導教員の担当科目を中心に、美術史を専門とする専任教員の授業を1年に1〜2科目ずつ履修して、3年間で最大24単位修得できます。内容やテキストは、毎年変更します。原則として、美術史の科目のみで修了単位は修得できます。
- フランス近代美術史特殊研究A(阿部成樹)…主に新古典主義美術を扱います。
- フランス近代美術史特殊研究B(阿部成樹)…履修者の研究テーマに合わせて研究発表の技法を発展させます。
- フランス近代美術史特殊研究A(泉美知子)…主に19世紀から20世紀のフランス美術史、文化遺産の歴史を扱います。
- フランス近代美術史特殊研究B(泉美知子)…主にフランス語美術史文献の読解を行います。
- 「インターンシップ(美術館実務研修)」(2単位)も受講可能です。
- その他、必要に応じて各種の語学科目や他の分野の科目を履修します。他専攻、協定のある他大学大学院の科目を8単位まで履修することができます。
学芸員資格と美術館インターンシップ
- 大学院では修得単位数が少ないため、並行して学芸員資格課程の授業を受講することができます。学部の授業ですので、履修にあたっては別途費用が必要です。文学研究科に入学した場合の履修料は、1単位あたり5千円です。実際に大学院で学芸員資格を取得し、専門職に就いた例が複数あります。
- 単位認定にふさわしいと判断された大学院生向けインターンシップ・プログラムを学外の美術館で受講することで、修士課程または博士課程の修了必要単位の一部(2単位)を修得することができます。学芸員職への実践的なトレーニングを積むことができます。
- インターンとしての採否は、美術館が決定します。必ず採用されるわけではありませんのでご留意ください。
入試
- 大学院文学研究科仏文学専攻として入試を行います。出願時に文学文化コースまたは美術史コースを選択しますが、入試自体は一括して行われます。なお美術史コースで学ぶには、仏文学専攻に入学する必要があります。他専攻からは学ぶことはできません。
- 大学院への入学試験(一般入学試験)は、秋季(修士課程のみ)と春季(修士課程・博士課程)に行われています。
 こちらにスケジュールが掲載されています。
こちらにスケジュールが掲載されています。 - 大学院入学試験(一般入学試験)では、全専攻共通の外国語科目からフランス語を受験します。試験中に辞書が使用できます。加えて専攻独自の専門科目を受験しますが、この科目では美術史関連の問題を選択することが可能です。フランス文学についての知識は必要ありません。
- 中央大学文学部からの内部進学のための特別選考制度(筆答試験は免除)もあります。
- 入学試験要項は、
 こちらからダウンロードできます。
こちらからダウンロードできます。 - 中央大学では毎年初夏と秋に、大学院進学相談会を開催しています。詳しくは
 こちらをどうぞ。
こちらをどうぞ。
学費
- 大学院の学費は、修士課程、博士課程で同一(年額約70万円)です。このほか、初年度のみ入学金(24万円)を要します。修士課程修了で約160万円、博士課程修了で約255万円の学費となります。ただし、学内からの進学(学部から修士課程、および修士課程から博士課程への進学)の場合は、学費減免等の措置があります。詳しくは
 こちらをご覧ください(*2025年度入試志願者用の情報です。今後変更があり得るのでご注意ください)。
こちらをご覧ください(*2025年度入試志願者用の情報です。今後変更があり得るのでご注意ください)。
リンク
- 入試についての情報は、
 こちらをどうぞ。
こちらをどうぞ。 「文系研究科入試広報サイト」(*文学研究科を含む、法学、経済学など文系研究科の紹介サイトです)もご覧ください。奨学金など各種情報が豊富です。なお、入学試験要項(募集要項)は、「文系研究科」(法学、経済学、商学、文学、総合政策)で合冊となっています。
「文系研究科入試広報サイト」(*文学研究科を含む、法学、経済学など文系研究科の紹介サイトです)もご覧ください。奨学金など各種情報が豊富です。なお、入学試験要項(募集要項)は、「文系研究科」(法学、経済学、商学、文学、総合政策)で合冊となっています。 - 中央大学大学院全体についての広報サイト
 「Focus」もご覧ください。研究計画書の作成アドバイスなどが掲載されています。
「Focus」もご覧ください。研究計画書の作成アドバイスなどが掲載されています。
科目等履修生|聴講生
- 大学院生として入学せず、科目等履修生、聴講生として、科目単位で学ぶことができます。科目等履修生は単位修得ができますが、聴講生については単位認定はありません。
- 入学試験はありません。書類審査(科目等履修生については、場合により口述試験を課すことがあります)で受け入れ可否を判断します。
- 募集は例年2月に行われ、認められれば4月から授業を受講できます。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。募集要項もダウンロードできます。
 科目等履修生募集|
科目等履修生募集| 聴講生募集
聴講生募集
在学生
- 2025年度現在、美術史を専門とする在学生は、修士課程5名、博士課程1名です。
進路|修了生紹介
- 「大学院文学研究科仏文学専攻美術史コース」在学生・修了生として、専門職への道を目指すことができます。
- 大学院修士課程修了後の専門分野への就職先は、以下の通りです。このほか、展示機材関連会社や一般企業、大学の事務職等に就職しています。
 藤田美術館(大阪)学芸員
藤田美術館(大阪)学芸員 泉美術館(広島)学芸員|
泉美術館(広島)学芸員| 卒業生紹介のページをご覧ください。
卒業生紹介のページをご覧ください。 跡見学園女子大学花蹊記念資料館 学芸担当
跡見学園女子大学花蹊記念資料館 学芸担当 多摩美術大学美術館学芸員|こちらの記事をご覧ください。
多摩美術大学美術館学芸員|こちらの記事をご覧ください。 活躍する修了生 渡辺眞弓さん
活躍する修了生 渡辺眞弓さん (株)キュレイターズ〔展覧会企画・運営・美術館コンサルティングなど〕|
(株)キュレイターズ〔展覧会企画・運営・美術館コンサルティングなど〕| 卒業生紹介のページに詳しい記事があります。
卒業生紹介のページに詳しい記事があります。- アートディーラー(オークショニア)
- 2023年度修了生(修士課程)齊藤唯衣さんの紹介記事が
 こちらにあります。ぜひご覧ください。
こちらにあります。ぜひご覧ください。
ブックガイド|美術史を学ぶために
- 大学院では、美術史研究を実践的に学びます。その基礎となるのは、西洋美術史の基本線を把握していることと、美術史学の考え方についての理解です。
- 美術史の知識とは、単に美術家や作品名をたくさん覚えることではありません。それを知っていることも有益ですが、ひとりひとりの作家、一点一点の作品を、大きな時代の流れに位置づけることができて、はじめて流れとしての美術史を見出したことになります。物知りな愛好家と美術史を専攻するあなたとの違いは、このように体系的な見方ができるかどうかという点にあります。
- 美術史の流れは、まず時代様式という大枠からなっています。古代、中世、近代、現代という大きな枠組みの中に、さらに古典期、ヘレニズム、初期中世、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、マニエリスム、バロック、ロココ、新古典主義…というように時代ごとの様式区分が設定されています。これらそれぞれの様式的な特徴と、それが基本的な枠組みであった時期を知る必要があります。その上で、重要あるいは典型的な作家・作品をこの流れの中に位置づけていきます。これが、美術史研究に臨む上での基本的な準備です。
- もうひとつの基本は、これまでの美術史学の考え方、美術史の書き方を知ることです。かたちと様式に注目する様式史、図像という意味の器の整理学としての図像学(イコノグラフィー)、その発展形としてのイコノロジーなど、美術史へのアプローチには歴史とヴァリエーションがあります。これらを知ることで、美術史を与えられた動かせないものとしてではなく、自分の視点から能動的にアプローチすることが可能になります。つまり、「勉強」から「研究」へと次元を移して学ぶことができます。
- 以下は、こうした基礎づくりのためのブックガイドです。美美コースでは必修科目の中で上記の基本を身につけられますが、特に他の専門分野から大学院美術史コースを目指す方々は、以下を参考にしてください。
- 高階秀爾・三浦篤 編『西洋美術史ハンドブック』 新書館、1997年|美美コースの各必修科目でテキストとして使用しています。上記のふたつの基本、つまり西洋美術史の骨格および代表的な作家・作品と、美術史学の主要な考え方について、簡潔にまとめてあります。末尾にある「西洋美術史学の方法と歴史」の章は美術史学の考え方(方法論)についての案内で、類書にはあまり見当たりません。簡便な専門用語集も付いていて便利です。
- ゴンブリッチ、E.H.(天野衛他訳) 『美術の物語』河出書房新社、2019年|定評ある西洋美術史の概説書。美術史の流れの根幹部分を捉え、それとの関連で精選された個別の作家・作品を取り上げており、専門研究を志す際の基本にするには好適です。なお出版社のサイトによれば、今秋にはポケット版を刊行予定とのことです。ゴンブリッチの著作は邦訳が多く、興味のあるものを手にするのもいいでしょう。
- ジャンソン、H. W. (村田潔、西田秀穂監訳)『美術の歴史』美術出版社、1995年|滔々と流れる美術史を大河小説のように描き切る、圧巻とも言える通史です。一気に通読するのもよく、また関心のある時代についてじっくり読むにも適しています。この本の主要部分を理解していれば、大学院での学修準備には十分です。*創元社刊行の簡略版とお間違えのないようご注意ください。
- 益田朋幸・喜多崎親 編『岩波西洋美術用語辞典』 岩波書店、2005年|専門用語について知りたい時、確認したい時に便利な辞典です。
- 『新潮世界美術辞典』新潮社、1985年|やや時代的な制約はありますが、個別の作家について知りたい時に便利です。
- ヴェルフリン、ハインリヒ(新田博衞訳)「美術作品の説明」 山崎正和編 『近代の藝術論』(中公バックス世界の名著81) 中央公論社、 1979年、 471-497 頁|美術作品を、それが制作された時代の表現様式を理解した上で見ることについて、平易に語る掌編です。
- クラーク、ケネス(高階秀爾、佐々木英也訳) 『ザ・ヌード 裸体芸術論 理想的形態の研究』ちくま学芸文庫、2004年|西洋美術の特質とも言える裸体表現について、時代を超えて自在に見通しをつけていく研究。年代順の作品の羅列という美術史のイメージから解放してくれる本でもあります。
- クラーク、ケネス(佐々木英也訳) 『風景画論』ちくま学芸文庫、2007年|西洋の風景画について広い視野から眺めわたし、その連続性とヴァリエーションを描き出す貴重な著作です。
- クラーク、ケネス(高階秀爾訳)『絵画の見かた』白水Uブックス、2003年|1章に1点を取り上げ、その作品の見かたの説明を試みていきます。単なる「解説」ではなく、読者とともに考える視点で書かれている点で、美術史の研究姿勢についての示唆を得られると思います。
- 「美術名著選書」岩崎美術社|西洋美術史の古典的な研究を邦訳した叢書です。図書館で少しずつでも覗いてみることをお勧めします。すぐに内容を理解できなくても、美術史研究の多様性と奥深さを感じられれば、十分な収穫です。
 こちらに一覧があります。
こちらに一覧があります。 - 『西洋美術研究』三元社|西洋美術史に特化した専門誌です。毎号、特集に基づく論文や充実した文献案内のほか、海外の展覧会紹介等もあり、有益です。
 こちらに既刊一覧があります。
こちらに既刊一覧があります。 - こちらのサイトで、お近くの図書館の所蔵状況を知ることができます。
 カーリル
カーリル
- フランス語学習のために|フランス語に初めて触れる方、既修でブラッシュ・アップしたい方は、以下を参考にしてください。目標があって学ぶ語学は、着実に進展するでしょう。
- 教育機関で学ぶ|フランス政府公式の語学学校・文化センター
- アリアンス・フランセーズ|パリを本部として世界展開するフランス語教育機関
- 自習で磨く