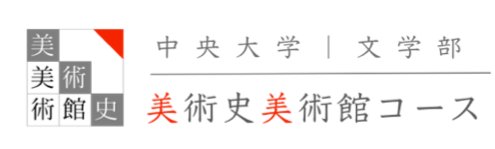美美コースには、西洋美術史と美術館・文化遺産の専門家によるゼミがふたつ開講されています。
阿部成樹ゼミでは、ゼミ生自身が議論を通じてテーマを設定し、美術館を訪ねながら美術史を学びます。
泉美知子ゼミでは美術史と、展覧会や美術館、文化遺産保護といった制度の歴史を見学をまじえて学びます。
以下では、阿部ゼミについてご紹介します(泉ゼミについては、こちらをご覧ください)。
指導方針
‣教室を飛び出そう:教室と都内各美術館のふたつのキャンパスがゼミの舞台です。教室での議論、発表と、学外見学を学修の重要な柱とします。
‣共同研究を楽しもう:受身の座学ではなく、全員参加の共同研究を行うゼミです。ひとつの共通テーマから自分たちの関心に基づいてサブテーマを引き出し、グループでの議論と美術館見学の企画立案・研究発表の実施を通じて自主的に学びます。2025年度のテーマは、「美術と食」です。詳しくは、すぐ下の「テーマ」の項目をご覧ください。
‣スキルを身につけよう:美術史と芸術文化についての専門的な知見を得るとともに、実社会への助走として自主性と協同性を涵養し、コミュニケーションの実践としてのプレゼンテーションやディスカッションに習熟することも目的としています。
テーマ
‣西洋美術史を自分に引きつける:
このゼミでは、わたしたちに身近なテーマを設定して、西洋美術史をゼミ生の「いま・ここ」に引きつけて探究することを目指します。遠い時代、遠い国の美術家とその作品は、いま、ここにいる私たちとどう触れ合うかを理解することで、ずっと身近な存在になるからです。
2025年度は、「美術と食」をテーマに共同研究を展開中です。食は人間にとってもっとも基本的な営みですが、同時に豊かな文化的意味を与えられてきました。このことは、各種のお祝いやお別れが、食事を伴うことにも明らかです。そして美術は、食とさまざまな接点を持ってきました。そこから、みっつのサブテーマを引き出します。1)食事の風景:人間の食の場面の多様性とは? 2)描かれた食材:食べ物を描くことの意味を、あらためて考えてみよう 3)食の空間:食べることを彩る空間の特徴を探ろう というみっつの問いです。その成果は、架空の展覧会カタログの制作を通じてアウトプットする予定です。もちろん、現実の美術館見学が、展示プランを立てる上でまたとないヒントになります。
美術が描き、またもたらしてきた「食」を考えることは、私たち自身の生活と環境を見直すことにつながるはずです。
‣いくつもの西洋美術史:
このように西洋美術史を自分に引きつけて考えるためには、美術の歴史はひとつではない、という前提から出発する必要があります。
今、YouTubeや新書で、西洋美術史の解説が人気を集めています。そこで解説されているゴシック、ルネサンス、バロックといった「時代様式」の歩みや、「何世紀に何が描かれた」という時系列に沿った年表は、美術の歩みを見出すための素材に過ぎません。
大学で学ぶ美術史は、自分の視点でこの素材から材料を選び、自分で編み上げることを学びます。「解説」に感心する(そしてすぐに忘れる)のとは違う、もっと能動的な面白さが、そこにはあります。
例えば女性像がどう変遷してきたか、家族はどう描かれてきたか、絵画の中で犬はどんな役割を果たしてきたか…あなたの視点や疑問に応じて、美術の歩みは変幻自在な姿を見せてくれます。歴史を学ぶとは、本来このようなものです。受け身に学ぶのではなく、創意工夫に基づいてひとつの物語を編み上げる楽しみを、ゼミと卒論で学びます。この学びは、大学でしかできません。
‣生きた場所としての美術館:
美術館は「陳列館」ではありません。もっとアクティヴな施設です。物言わぬ作品と来館者の橋渡しをするために設備と展示に工夫し、またアイディアを競ってさまざまな活動を展開しています。特に近年注目されているのは、「ラーニング(教育普及活動)」です。子供から高齢者まで、健常者から障がいあるいは病気によるハンディを負った人まで、できるだけ広い範囲の観客に美術を楽しんでもらい、人生に豊かな時間を付け加えることを目的とする分野です。それは単なる「解説」を超えて、楽しめる教材を開発し、誰もが積極的に美術に関われるような企画を模索し展開しているのです。その場には、美術作品をめぐるさまざまな思いが交錯しています。
このゼミでは、こうした活動を担う学芸員の視点を知ることで、受け身の「観客」の限界を超えて美術館を知り、体験します。このことは、社会に出てから美術館に限らずさまざまな分野で役立つでしょう。
議論する
‣このゼミでは、ゼミ生が主役です。各自の関心に基づき班に分かれて共同研究を行い、テーマ設定や企画の実施にあたります。議論の様子は教員やTA(ティーチング・アシスタント:大学院生が務めます)が見守り、助言します。個人個人の興味は、卒業論文で深く掘り下げます。
発表する
‣ゼミでは、ゼミ全体で共通のテーマについて議論して班ごとのテーマを設定し、そのテーマについて前期末にゼミ生に向けてプレゼンテーションします。
‣後期にそのテーマについての研究発表を行います。スライド、配付資料を準備し、交代で講師やタイムキーパーを務め、実りある発表を目指します。すべて教員がバックアップします。
見学する
‣各班の研究テーマに関連する見学先を議論して決め、その結果を前期末にゼミ生に向けてプレゼンテーションします。
‣後期に美術館見学を組織します。ゼミ生・見学先への連絡、事前のレクチャー、当日のオーガナイズ、事後レポートのテーマ設定などが各班のタスクです。すべて教員がバックアップします。
招く
‣時に外部講師を招いてレクチャーしていただくこともあります。
つながる
‣スマートゼミ:共同作業を円滑に進めるため、主にGoogleによるサービスを利用して資料・予定の共有、共同編集やミーティングを効率的に行います。卒論の学修と指導にもGoogleドキュメントを利用して、卒論ノートを教員と共有します。
‣お互いを知るために、新人歓迎会、各期末お疲れ会など定例の行事があります。
旅する
‣夏季休暇には、関東圏外へ見学旅行を行っています(自由参加)。詳しくは「夏季見学旅行」のページへ。
留学する
‣ゼミの中途で、留学することもできます。留学先で修得した単位をゼミの単位として認定することもできるので、同級生と同じ年度に卒業することも可能です。
‣美術史の基礎を学んでから留学することで、語学留学とはひと味違う留学ができます。
‣夏季休暇中に、ヨーロッパやアメリカの各大学で開講される美術史の夏季プログラム(多くは1〜2週間)に参加するのもおすすめです。
執筆する
‣3年次の末から、教員とマンツーマンの卒論指導を開始します。テーマ設定から資料集め、目次の組み立て、草稿執筆まで、共に進めていきます。途中、ゼミ内で構想発表、中間発表を行い、ゼミ生の意見を参考にします。
‣卒論では、絵画や建築の他に、写真や工芸、デザイン、ポスターなども取り上げることができます。あなたの関心を生かしてください。
‣優れた卒論の要旨は、『中大仏文研究』(中大仏文研究会、年1回刊行)に掲載されます。
‣2022年度の卒論テーマ:シャルダンの風俗画と18世紀フランスの家族 観 ──シャルダンが描く私的空間──/AI時代に描くということ ──画像生成 AI と画家の存在意義について──/横尾忠則と西洋美術 ──「分かれ道」のモチーフを中心に──/機能主義と椅子 ──バウハウスからデンマーク・デザインまで──/17 世紀オランダ静物画と資本主義 ──ジャンルの確立と受容について──/ヒエロニムス・ボスが描いた幻想世界の研究 ──三連祭壇画における世界の終末描写を中心に──/《回顧的女性胸像》を通してみる
サルバドール・ダリの可食的モチーフ/美術館体験の変化と可能性 ──建築の視点から──/《画家のアトリエ》に見る
クールベのレアリスム/ボッティチェリとパトロネージ ──ロレンツォ・デ・メディチが果たした役割について──/視神経の冒険 ──ピエール・ボナールの室内情景と風景表現──/ギリシア神話から見るモローの死生観/宮廷画家ジュゼッペ・アルチンボルド ──肖像画と奇想のあわい──/ココ・シャネルのジュエリーが鮮やかな理由 ──西洋金属工芸の歴史から探る──/19 世紀後期のブルジョワ女性の視線 ──ベルト・モリゾの女性像から──/日本近代美術と印象派 ──黒田清輝とラファエル・コランを中心に──/『芸術の日本』に見る北斎 ──フランスにおける浮世絵版画受容の一側面──
‣2021年度の卒論テーマ:アングル作品に見るジェンダー観 ──ダヴィッド、ドラクロワとの比較を中心に ──/キリスト教の礼拝像イコンについて ──初期キリスト教からイコノクラスムまで ──/地域に育つ美術館 ──長野県を例に──/日本における日本のアール・ブリュットの展開 ──知的障がい者が描くアートの今と可能性 ──/フェルメールの視点 ──《デルフトの眺望から見る事実と理想の風景表現》──/近代美術と観衆 ──18 世紀フランスから現代日本まで ──/ドラクロワと社会/シャガールの絵画に見られるユダヤ人アイデンティティ/ユベール・ロベールの⾵景画における⾵俗的モチーフをめぐって
メンバー
‣ゼミ生は例年、3、4年生合わせて20〜30名程度です。
進路・就職
‣ゼミ生の進路は、美術関連に限られません。食品、IT、交通(鉄道、航空)、旅行、放送(テレビ)、国家公務員、地方自治体、アパレル、広告、出版、金融、図書館司書、声優など様々な分野に就職しています。
‣専門職としては、多摩美術大学美術館学芸員、藤田美術館学芸員、泉美術館学芸員、(株)キュレイターズ(展覧会企画)、(株)ブレーントラスト(展覧会企画)、(株)Konel(クリエイター集団)に進んでいます。
‣進学先としては、中央大学大学院、東京藝術大学大学院(国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻)に進んでいます。
‣卒業生紹介のページもご覧ください。